なぜワクチンの種類が違うと副反応の種類も違ってくるのか
2021/10/23 18:50:00 |
ワクチン熟考 |
コメント:0件
前回の子宮頸癌ワクチンが接種後1年以上経過してから症状を出す理由を考えていた時に、ひとつ新たな疑問にぶち当たりました。
もしもワクチン接種後の長期的な副反応が、「異物除去反応システムのオーバーヒート」で生み出されているのだとすれば、
その症状はワクチンの種類に関わらず、同様の症状が引き起こされていなければつじつまが合わない、ということにならないでしょうか。
しかし実際には例えばコロナワクチンで起こってくる副反応、子宮頸癌ワクチンで起こってくる副反応、麻疹ワクチンで起こってくる副反応・・・、それぞれワクチンの種類によって起こってくる副反応には少し特徴の違いがあります。
接種部位疼痛、発熱、倦怠感など、よくある急性期の副反応はどのワクチンでも似たり寄ったりだと思いますが、稀に起こってくる事象には明確な違いが観察されます。
子宮頸癌ワクチン接種後の長期的な副反応としては四肢の疼痛が非常に特徴的です。私も実際にそのような患者さんを診たことがありますが、血圧を測る時のマンシェットを巻く時でさえ非常に痛がるような状況でした。
一方でコロナワクチンでは心筋炎の副反応があることが話題となっていますし、麻疹ワクチン(麻疹・風疹混合ワクチン)の場合はADEM(Acute Disseminated encephalomyelitis; 急性散在性脳脊髄膜炎)と呼ばれる脳炎が稀に起こることはよく知られています。
もしもワクチン接種後の副反応が、ワクチン接種を契機にもたらされた宿主側の異物除去反応システムのオーバーヒートが原因であるとするならば、このような違いが出て来るという事実に矛盾が出てこないでしょうか? この矛盾を解消する鍵となるヒントは2つあると思っています。
1つは「ワクチン接種後の副反応は、ワクチンが予防対象とするターゲットの感染症の症状と似ている」という客観的事実、もう一つは私が過去考察で導いた「ウイルスとは自己と他者の中間的な存在だという仮説」です。
まず前者から行くと、例えばインフルエンザワクチン接種後に、インフルエンザ様の症状を発症される方がおられます。
この現象の理由について「インフルエンザワクチンを打つという行為が、疑似的にインフルエンザにかからせるようなものだから」という説明がよく用いられます。
ただ今回mRNAワクチンという新技術が用いられたコロナワクチンに関して言えば、この説明のしかたはちょっと当てはまりません。
なぜならばワクチンで注入したものは病原体に似せた抗原ではなく、遺伝子(mRNA)という病原体とは似て非なる物質であるからです。
それなのに、コロナワクチン接種後に起こってくる心筋炎という現象は、実際のコロナ感染でも稀に起こってくることがわかっています。これは単なる偶然でしょうか?
他にも例はあります。例えばおたふくかぜ(ムンプス)ワクチンです。おたふくかぜにかかると稀に無菌性髄膜炎という合併症が引き起こされることが知られていますが、
おたふくかぜ(ムンプス)ワクチンの接種後にも稀に無菌性髄膜炎という現象が引き起こされることがわかっています。偶然が重なる時は偶然ではないと考える方が自然です。
これが偶然ではなく、必然だと仮定した場合、少なくとも「病原体類似の物質の注入だから病原体由来の感染症の症状が起こりうる」という説明は、コロナワクチンの場合がそうではないために、不適切です。
では何が理由でこの現象が必然になっているのかということを説明するために、もう一つの「ウイルスは自己と他者の中間的な存在である」という考えが必要になってきます。
コロナワクチンというのはスパイク蛋白質というウイルスの表面に位置する一分子を作らせるという離れ業を可能にしているワクチンです。
この離れ業がコロナ様の症状を引き起こしているのだとすれば、まずはこのスパイクタンパク質に対する抗体が悪さをしているのではないかという考えが頭に浮かびます。
専門家の報告によれば、mRNAワクチン接種後のスパイク蛋白質産生は数週間以内でなくなると言われ、また現時点でスパイク蛋白質に対するワクチン接種後の抗体価は3ヵ月でピーク時の4分の1に減衰するということが示されています。
もしもスパイク蛋白質に対する抗体が原因で副反応が起こっているのであれば、こうした増減にリンクして症状が消失しているはずです。これは接種後1週間以内に副反応が多いという事実とリンクしているように思え、一見矛盾がありません。
しかし「コロナ後遺症(LONG COVID)」と呼ばれる状態も同じようにコロナのスパイク蛋白質への抗体が引き起こされていると考えると、1年以上経ってもその症状が持続している事実に対して、1年以上経てば平常時レベルまで減衰しているであろう抗体の挙動と矛盾します。
そこでもう一つの発想として「ウイルス成分と親和性のある細胞の過活動によって感染症の症状とワクチン後の副反応は引き起こされている」という仮説を私は提唱します。
例えばコロナウイルスもしくはコロナウイルスのスパイク蛋白質と親和性のある細胞というのはACE2受容体というものを持った細胞です。
一般的には「コロナウイルス(の表面にあるスパイク蛋白質)はACE2受容体を鍵に人体に入り込む」というように、ウイルス側の巧妙な手口であるようにACE2受容体のことが紹介されがちですが、
以前、プロレスの大技でたとえましたように、ウイルスが感染し増殖するという現象はウイルスの巧妙な手口というよりは相手側の協力なくしては成立しない見事なチームワークだとしか私には思えません。
ということは「コロナウイルス(あるいはスパイク蛋白質)とACE2受容体は、はなからグル」とまで表現してしまうと恣意的ですが、少なくとも互いに親和性のある物質どうしだという考えも成り立つと思います。
さてそんな状況の中でコロナウイルスやスパイク蛋白質が大量に入り込むとどうなるでしょうか。
ACE2受容体と同様の仲間、すなわち「自己」分子だと認識されているうちは何も起こらないでしょうけれど、それが不自然なくらいに大量に入り込んできたり、あるいは内側から大量に産生されるようになれば、それは「他者(非自己)」と認識されることが起こりえると思います。
これは普段の血糖値であれば全体としてシステムが非常に落ち着くにも関わらず、その血糖値が大量に入ってくると急にシステム全体が活性化して、それを鎮めるシステムが急速に動員される現象とリンクします。
「自己」分子だと完璧に認識される「ブドウ糖」でさえそうなのですから、「ウイルス」のような「自己」と「非自己」の中間的な存在となればシステムのオーバーヒート状態はさらにこじれることが容易に想定できます。
要するに単なる「自己分子の一時的な暴走」という非日常現象が出現して収束するということに留まらず、「非自己」を誤って「自己」と認識してしまうことによって、常時存在している「自己」分子までもが攻撃対象となってしまい、非日常現象が常態化してしまうということです。
この時に真っ先にオーバーヒートしてしまうのは、ACE2受容体のある細胞達です。ACE2受容体は、とある研究論文によりますと全身の細胞に分布しており、例えば、呼吸器系では、鼻腔の粘膜上皮細胞に強く発現するとともに気管、気管支、肺胞と末梢に移行するに従い減少するという特徴があります。
また呼吸器系以外では、小腸上皮細胞、血管内皮細胞、腎尿細管、心血管、精巣、卵巣にACE2受容体が発現していることがわかっています。
さらに免疫系ではマクロファージにという血液細胞にACE2 が発現していますし、神経系では嗅神経の支持細胞(sustentacular cells)にもACE2が発現しています。
嗅神経にACE2が存在することは、コロナ感染で嗅覚障害が出現する理由としても説明可能ですが、それは一般的には「コロナが自己細胞に侵入してダメージを加える」というようなイメージで受け止められているかと思います。
ところが実はコロナウイルスは「自己」的な細胞で、システムが誤ってこれを「非自己」と捉えて攻撃する体制になったと考えたらどうでしょうか。
「コロナ」や「スパイクタンパク質」を攻撃する抗体が過剰産生されるとともに、「コロナ」や「スパイクタンパク質」を認識するACE2受容体を持つ「自己」細胞も連動して過活動状態に陥ります。
そうなると嗅覚神経細胞の過活動の結果、嗅覚障害が出るというストーリーも見えてきます。つまり「コロナ」ウイルスが悪さをして嗅覚障害が出るのではなく、自分のシステムの過活動の結果として嗅覚障害が出るのです。
そう考えるとコロナ感染やコロナワクチンで稀に心筋炎が引き起こされる理由も説明します。コロナウイルスは血液中を循環して何とか心筋細胞までたどり着いて心筋炎を起こすのではなく、全身のACE2受容体含有「自己」細胞が活性化されていく中で稀に受容体の発現頻度の低い心筋細胞にまで過活動が及ぶ結果、心筋炎が引き起こされるということです。
そう考えると、世間的にはデマだと切り捨てられている「コロナワクチンで不妊になる可能性がある」というのも、ACE2受容体が精巣や卵巣にもある以上、理論的にはあながち間違いとも言い切れず、過活動によって機能障害に陥る可能性は十分にあると言えるでしょう。
そして、これがワクチン接種によって引き起こされるシステムのオーバーヒートの症状パターンが、ワクチンの種類によって変わるということを説明する理屈になると思います。
もう一つ、この話をおたふくかぜを起こすムンプスウイルスに応用してみましょう。
ムンプスウイルスが人体に侵入するには、α2,3―結合型シアル酸を含む3糖「シアル酸」-「ガラクトース」―「グルコース」の[N-アセチルグルコサミン]構造が必要であるようです。
「N-アセチルグルコサミン」とは何かと調べると、細菌の細胞壁を構成する成分で、人体においては痛みに関わる非定型的な神経伝達物質として関わっているという情報がありましたが、
一番有名なところでは、「N-アセチルグルコサミン」と「グルクロン酸」という物質の2つが結合することで、皮膚や関節の構造を作ることで有名な「ヒアルロン酸」になるというのがあります。従って、「N-アセチルグルコサミン」という物質は関節や皮膚を中心に人体に広く分布しているということになります。
それで、おたふくかぜと言えば両側の耳下腺が腫れることが有名です。では耳下腺にN-アセチルグルコサミンがあるのかと調べてみると、どうやらしっかりあるようです。
そしておたふくかぜの稀な合併症、及びおたふくかぜワクチンの稀な副反応として「無菌性髄膜炎」があるというのは前述の通りです。そうなると髄膜に「N-アセチルグルコサミン」があるのかという点が気になります。
調べると、「脳型トランスフェリン」という髄液産生装置である脈絡叢という部分から分泌される物質に「N-アセチルグルコサミン」が含まれているという情報を得ました。
「脳型トランスフェリン」という言葉、実は私は聞き覚えがあります。髄液の吸収不全が原因で発症する正常圧水頭症という病気の診断マーカー候補で、これに糖鎖の修飾が関わっているという内容のブログ記事を書いた時に出てきた物質名です。
2015年に書いていたブログ記事ですが、まさかこの時の糖鎖が「N-アセチルグルコサミン」で、ここに来てつながるとは想像だにしていませんでした。ということはN-グルコサミンは脈絡叢にも存在していることになり、脈絡叢は髄膜ともつながっていますから、ムンプスウイルス及び類似構造物に刺激された「N-アセチルグルコサミン」含有細胞の過活動が「無菌性髄膜炎」の発症につながっても不思議ではないというストーリーに、ここでも矛盾はありません。
では最後に、子宮頸癌ワクチンに話を応用してみるとどうでしょうか。子宮頸癌の原因とされるヒトパピローマウイルスは何を手掛かりに「自己」細胞に侵入するのでしょうか。
ところがなんとヒトパピローマウイルスの侵入経路は、コロナのACE2受容体のようにはっきりとはされていないようなのです。とある研究報告によるとHPV BP-1というタンパク質が受容体の候補分子として挙がっているようですが、このHPV BP-1というタンパク質がどこにどのように分布しており、どのような機能を持っているのかに関しては調べきることはできませんでしたし、あくまでも候補の1つなのでこれだけが侵入経路となっているのかも断言しきれません。
つまり子宮頸癌ワクチンというウイルス類似物で活動が刺激されうる自己細胞の詳細がわからないのです。
しかしヒトパピローマウイルスが感染して起こる現象を観察することで、細かい分子はわからずとも、だいたいどの辺りの細胞と親和性があるのかをつかむことは可能です。
ところがヒトパピローマウイルスの遺伝子型には100種類以上のものがあり、子宮頸癌の原因として有名な16型、18型以外にも多数の亜型が存在しています。
子宮頸癌以外にヒトパピローマウイルスによって引き起こされるとされる病気をざっと挙げてみますと、最も有名なのは皮膚のイボ(乳頭腫)(※「パピローマPapilloma」がもともと「乳頭腫」の意味)ですが、それ以外にも口腔、生殖器などの扁平上皮に接触感染し、中咽頭がん、肛門癌、陰茎がん、膣がん、外陰がんなどの別のがんにかかるリスクも上がるとされています。
それらを踏まえると、ヒトパピローマウイルスと親和性のよい自己細胞は皮膚や皮膚に近い消化管(口腔、肛門)、生殖器に共通して存在する分子を持つ細胞なのかなという辺りをつけることができますが、
一方で子宮頸癌ワクチン接種後の後遺症として「HANS(HPV vaccine-associated Neuroinflammatory Syndrome;子宮頸がんワクチン関連神経免疫異常症候群)」という概念の状態があることもよく知られていますので、
子宮頸癌ワクチン接種後の後遺症として若い女性に四肢疼痛、記憶障害が生じうる事実を踏まえますと、頻度は低くとも神経細胞もヒトパピローマウイルスの感染対象となっていれば説明がつきそうなものですが、
現在までにヒトパピローマウイルス感染症の中で神経に主たる異常をきたす病気は特に知られていません。
以前、「HANS」が「機能性身体障害」なのか、それとも「脳の病気」なのかについて医学界の中で侃々諤々の議論が行われた際に、
「ヒトパピローマウイルスの表面タンパク質(L1蛋白)と神経組織に分子相同性はない」という実験結果を示されたドクターがおられました。
だからHPVワクチンを打つことで、この成分に交差免疫が働いて脳や神経に炎症が起こるということはあり得ないという主張なのだと思いますが、
私の今回の仮説を踏まえれば、その実験結果ではまだワクチン接種でHANSが起こりえないとは言い切れないということになります。
なぜならば、ワクチンと自己組織の相同性があるかどうかが問題なのではなく、ヒトパピローマウイルスにも子宮頸癌ワクチンにもともに刺激される特定の分子を持つ「自己組織」がどこに分布しているかが重要であるからです。
ひょっとしたら主として神経が障害される病気の患者さんで、ヒトパピローマウイルスの感染があるかどうかを調べたら、感染歴を確認することができるのかもしれませんが、少なくとも文献上でそうした事実を確認することはできません。
しかし今までの仮説での流れを考えれば、子宮頸癌ワクチン接種で四肢疼痛や記憶障害などの神経細胞の障害が示唆される症状が稀ながら起こっているのであれば、
ヒトパピローマウイルスの侵入経路となる分子が神経組織にも存在している可能性を検討する必要があると私は思います。
そしてそこがはっきりするまでは子宮頸癌ワクチンの接種を安易に積極的勧奨再開すべきではありません。
事実、例えば多発性硬化症という神経の病気には何らかのウイルス感染が関わっているという説があり、はっきりとそのウイルスが同定されているわけではない一方で、子宮頸癌ワクチン後遺症の方の中には多発性硬化症のような症状を呈する方もおられるところまではわかっています。これは決して無視できない事実です。
最後に今回のこの仮説のもう一つ信頼に足るところをお示しします。
この仮説の長所は「ワクチン毎に副反応の性質が異なることを説明できる」という点のみならず、
「ワクチン接種後の副反応が全員に起こるわけではないことの説明にもなる」という点も大きなところだと思います。
もしもワクチン中の何らかの成分が、自己免疫反応を引き起こして重度の後遺症をもたらしているということになれば、
同じワクチンを打った圧倒的大多数の人で同様の現象が起こっていないという事実が非常に不自然なことになります。
この頻度の稀さが、ワクチン推進派が重度副反応の存在を軽視しようとするひとつの大きな要因でもあるわけですが、少数でも事実は事実です。そこには必ず理由が存在するはずです。
その理由をこの仮説でもって、ワクチンの成分ではなく、「ワクチンとウイルスによって共通で刺激される自己細胞の感受性(生体内環境)の違い」と考えれば、稀に重度副反応が起こる理由はつじつまがあいます。
なぜならば、基本的にウイルスとワクチンで刺激されうるけれども、人体の中での量や分布が少ない細胞であればよほどシステムがオーバーヒートされない限りは過活動にならないという部位が存在するはずだからです。
コロナワクチンで言えばそれが心筋、ムンプスワクチンで言えばそれが髄膜(脈絡叢)、子宮頸癌ワクチンで言えばそれがひょっとしたら脳神経細胞、ということになると考えることができます。
逆に言えば、そのような希少な自己細胞までもが刺激されてしまうような人には、それくらい過活動になりやすいという何らかの宿主側の要因が存在するという話となり、
必ずしも一方的にワクチン接種だけが原因というわけではないという話にもつながっていきますし、
重度の後遺症を回復させていく希望も、済んだワクチンについて四の五の悩むのではなく、
今の自分のオーバーヒート状態をいかに冷まし、整えていくべきかを考えるという治療方針の見通しまで見えてきます。
今回の仮説が正しければ、ワクチンが賛成か反対かの二項対立構造に陥るのではなく、
リスクとベネフィットを勘案して、各人がよく考えて接種すべきかどうかを判断すべき完璧ではない医療行為だという認識へとつなげていくことができます。
難しい話だったかもしれませんが、とても重要なところなので力を入れて書かせて頂きました。
たがしゅう
リンク
プロフィール
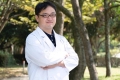
Author:たがしゅう
本名:田頭秀悟(たがしら しゅうご)
オンライン診療医です。
漢方好きでもともとは脳神経内科が専門です。
今は何でも診る医者として活動しています。
糖質制限で10か月で30㎏の減量に成功しました。
糖質制限を通じて世界の見え方が変わりました。
今「自分で考える力」が強く求められています。
私にできることを少しずつでも進めていきたいと思います。
※当ブログ内で紹介する症例は事実を元にしたフィクションです。
最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
- 2024/04 (7)
- 2024/03 (7)
- 2024/02 (6)
- 2024/01 (8)
- 2023/12 (9)
- 2023/11 (7)
- 2023/10 (8)
- 2023/09 (5)
- 2023/08 (9)
- 2023/07 (4)
- 2023/06 (5)
- 2023/05 (5)
- 2023/04 (7)
- 2023/03 (7)
- 2023/02 (5)
- 2023/01 (7)
- 2022/12 (5)
- 2022/11 (4)
- 2022/10 (11)
- 2022/09 (6)
- 2022/08 (6)
- 2022/07 (5)
- 2022/06 (6)
- 2022/05 (4)
- 2022/04 (5)
- 2022/03 (5)
- 2022/02 (4)
- 2022/01 (7)
- 2021/12 (14)
- 2021/11 (4)
- 2021/10 (10)
- 2021/09 (10)
- 2021/08 (8)
- 2021/07 (14)
- 2021/06 (11)
- 2021/05 (17)
- 2021/04 (9)
- 2021/03 (8)
- 2021/02 (9)
- 2021/01 (14)
- 2020/12 (9)
- 2020/11 (7)
- 2020/10 (6)
- 2020/09 (9)
- 2020/08 (11)
- 2020/07 (20)
- 2020/06 (22)
- 2020/05 (18)
- 2020/04 (22)
- 2020/03 (10)
- 2020/02 (7)
- 2020/01 (5)
- 2019/12 (9)
- 2019/11 (19)
- 2019/10 (31)
- 2019/09 (6)
- 2019/08 (7)
- 2019/07 (7)
- 2019/06 (13)
- 2019/05 (21)
- 2019/04 (9)
- 2019/03 (13)
- 2019/02 (15)
- 2019/01 (28)
- 2018/12 (9)
- 2018/11 (2)
- 2018/10 (11)
- 2018/09 (30)
- 2018/08 (31)
- 2018/07 (31)
- 2018/06 (31)
- 2018/05 (31)
- 2018/04 (30)
- 2018/03 (31)
- 2018/02 (29)
- 2018/01 (31)
- 2017/12 (31)
- 2017/11 (30)
- 2017/10 (32)
- 2017/09 (31)
- 2017/08 (31)
- 2017/07 (32)
- 2017/06 (31)
- 2017/05 (31)
- 2017/04 (31)
- 2017/03 (31)
- 2017/02 (29)
- 2017/01 (32)
- 2016/12 (31)
- 2016/11 (30)
- 2016/10 (31)
- 2016/09 (15)
- 2016/08 (11)
- 2016/07 (5)
- 2016/06 (10)
- 2016/05 (8)
- 2016/04 (5)
- 2016/03 (5)
- 2016/02 (10)
- 2016/01 (10)
- 2015/12 (7)
- 2015/11 (8)
- 2015/10 (7)
- 2015/09 (6)
- 2015/08 (6)
- 2015/07 (5)
- 2015/06 (5)
- 2015/05 (5)
- 2015/04 (3)
- 2015/03 (10)
- 2015/02 (28)
- 2015/01 (31)
- 2014/12 (31)
- 2014/11 (31)
- 2014/10 (31)
- 2014/09 (29)
- 2014/08 (53)
- 2014/07 (31)
- 2014/06 (30)
- 2014/05 (31)
- 2014/04 (30)
- 2014/03 (31)
- 2014/02 (28)
- 2014/01 (31)
- 2013/12 (32)
- 2013/11 (30)
- 2013/10 (33)
- 2013/09 (39)
カテゴリ
メールフォーム
スポンサードリンク
検索フォーム
ステップメール
QRコード


コメント
コメントの投稿